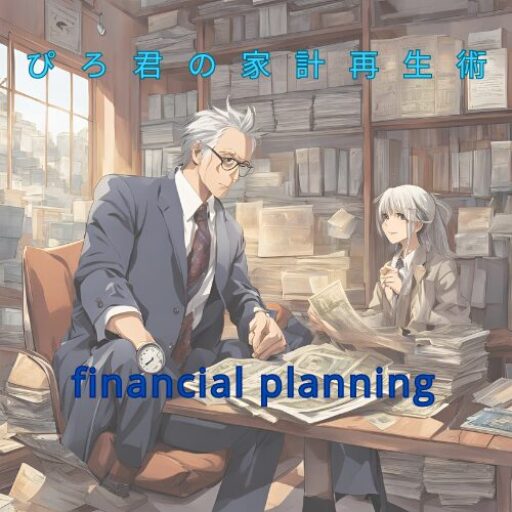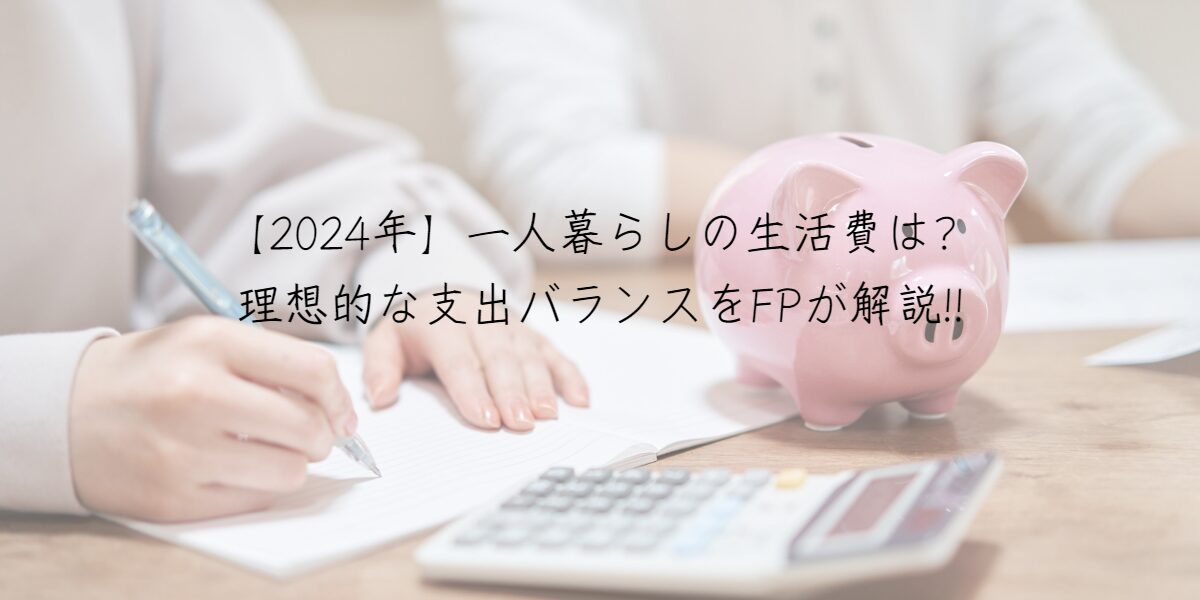こんにちは、ぴろ君です。
初めての新生活、新たな環境、新天地に胸躍りますよね。同時にうまくやっていけるか不安も募るのではないでしょうか。右も左もわからない。そんな状態であるにも関わらず、経済的にもゆとりある生活が送れるか心配になるものです。
そこで今回は「一人暮らしに生活費」と、「理想的な支出バランス」についてAFPであるぴろ君がデータを基に紐解いてご紹介します。ご自分の現在の生活に当てはめれば、安定した理想的な生活を手にすることができるでしょう。
この記事のポイント
☑一人暮らしの生活費の基準が分かる!!
☑理想的な生活の支出バランスが分かる!!
☑節約の手段が分かる!!
☑安定した生活バランスが分かる!!
一人暮らしの生活費の平均額は159,552円

総務省統計局の家計調査で遡れた12年分の平均額は「159,552円」でした。
下記の表は各年の平均消費支出額です。2022年は161,753円。コロナウィルスの猛威が収束に向かいつつあり、自粛ムードから解放されたことで消費支出が増えたのでしょう。実際問題コロナウィルスが騒がれ始めた2020年は過去12年間で最も少ない消費支出となっています。
| 年 | 消費支出額 | 食費 | 光熱費 | 被服費 | 保険医療 | 交通費 |
| 2022 | 161,753円 | 39,069円 | 13,098円 | 5,047円 | 7,384円 | 19,303円 |
| 2021 | 155,046円 | 38,410円 | 11,383円 | 4,606円 | 7,625円 | 18,856円 |
| 2020 | 150,506円 | 38,257円 | 11,686円 | 4,692円 | 7,029円 | 18,217円 |
| 2019 | 163,781円 | 40,331円 | 11,652円 | 5,720円 | 7,666円 | 20,989円 |
| 2018 | 162,833円 | 40,026円 | 11,847円 | 5,312円 | 7,175円 | 21,537円 |
| 2017 | 161,623円 | 39,649円 | 11,380円 | 5,661円 | 7,044円 | 18,825円 |
| 2016 | 158,911円 | 39,808円 | 11,028円 | 5,554円 | 6,720円 | 18,640円 |
| 2015 | 160,057円 | 40,202円 | 11,667円 | 6,512円 | 7,107円 | 18,717円 |
| 2014 | 162,002円 | 38,539円 | 11,849円 | 6,404円 | 6,962円 | 19,681円 |
| 2013 | 160,776円 | 37,831円 | 11,863円 | 5,818円 | 6,907円 | 19,769円 |
| 2012 | 156,450円 | 37,726円 | 11,404円 | 5,880円 | 6,640円 | 18,979円 |
| 2011 | 160,891円 | 37,775円 | 10,875円 | 6,392円 | 6,216円 | 19,500円 |
https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_mr-y.pdf
家計調査 家計収支編 単身世帯
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200561&tstat=000000330001&cycle=7&month=0&tclass1=000000330001&tclass2=000000330022&tclass3=000000330024&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3Atclass3%3Acycle&tclass4val=0
一人暮らしの生活費の内訳と理想的な支出バランス

消費支出額より算出したデータから支出バランスを求めると次の通りになります。データを基に理想的な支出バランスを作っていきましょう。交通費が掛からない場合はそのまま貯蓄に回すと、より安定した生活環境を構築することができます。
食費 :23~25%
光熱費 :7~8%
被服費 :3~4%
保険医療:4~5%
交通費 :12~13%
| 年 | 消費支出額 | 食費 | 光熱費 | 被服費 | 保険医療 | 交通費 |
| 理想支出バランス | ‐ | 23~25% | 7~8% | 3~4% | 4~5% | 12~13% |
| 2022 | 161,753円 | 24% | 8% | 3% | 5% | 12% |
| 2021 | 155,046円 | 25% | 7% | 3% | 5% | 12% |
| 2020 | 150,506円 | 25% | 8% | 3% | 5% | 12% |
| 2019 | 163,781円 | 25% | 7% | 3% | 5% | 13% |
| 2018 | 162,833円 | 25% | 7% | 3% | 4% | 13% |
| 2017 | 161,623円 | 25% | 7% | 4% | 4% | 12% |
| 2016 | 158,911円 | 25% | 7% | 3% | 4% | 12% |
| 2015 | 160,057円 | 25% | 7% | 4% | 4% | 12% |
| 2014 | 162,002円 | 24% | 7% | 4% | 4% | 12% |
| 2013 | 160,776円 | 24% | 7% | 4% | 4% | 12% |
| 2012 | 156,450円 | 24% | 7% | 4% | 4% | 12% |
| 2011 | 160,891円 | 23% | 7% | 4% | 4% | 12% |
家賃の理想は収入の25%を目標にする
家賃は基本的に3割までが上限となります。これは「入居審査の基準をクリアする目安」とされおり、「家賃を支払っても生活費を確保できる」水準を満たすためです。
よって、3割を超えるような住居は不動産業者の審査をクリアすることができず、入居は困難となります。したがって目標としては25%程度とするのが良いでしょう。また、25%にしておくことで固定費の削減も盛り込んでいます。
20万円の手取りがある場合を例に考えてみましょう。
・20万×30%=6万
・20万×25%=5万
毎月1万円を家賃に支払うか、それとも貯蓄や娯楽などに支払うか。どちらが有意義でしょうか。年間で12万円も浮くわけですから、この5%はとても大きいと考えます。
経費は毎月必ず支払うことになるですから、最大限抑えましょう。
先取り貯金の理想は15%
貯金は先取りで15%を目安に別口座に移動するか、定期預金などに預け入れましょう。貯金を作る際、毎月余った額から貯金を作る方がいらっしゃいます。それで成功されている方もいますが、難易度は高めです。
恐らくは貯金よりも優先したいことがあって「余ったら」と考えるのではないでしょうか。よって、貯金は先取りで取り置きし、残金でどのようにやりくりをすべきかを検討すべきです。
このように切り分けを行うことで、理想的な貯金を作り上げることが可能になります。
理想に近づけるために食費はムリに削らない
食費を削るのはNG行為です。支出バランスと比較して多く使っていないなら、ムリに削る必要はないでしょう。
ムリに食費を削った生活にすると、あとで反動がきて、結果として高額になる恐れがあります。反動から過食し、食費がかさんだり、娯楽やその他生活費に回るといった具合です。
節約はムリなく適度に行うべきです。ムリな節約から体調の悪化や、生活バランスの乱れの原因となりますので注意しましょう。
一人暮らしの生活防衛資金の目安は、生活費3ヶ月分~半年分
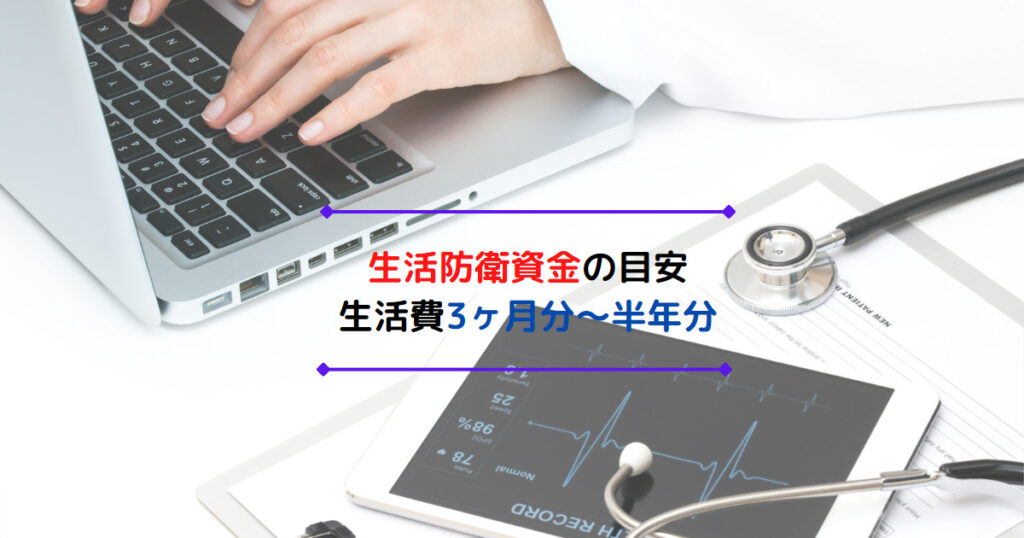
今は健康でも突然のケガや病気、会社の倒産、巻き込まれ事故など。一人だからこそ、何があるか分かりません。何があっても対応できるように、自分の身を守れる程度の資金は用意しておきましょう。
一人暮らしの生活防衛資金の目安は、生活費3ヶ月分~半年分は必要です。2022年の消費支出は年間平均で「161,753円」です。
この3~6倍なので、「485,289円~970,518円」が万一に備えた生活防衛のラインとなります。

生活費を抑える最大のコツは固定費を抑えること

家賃でも述べたように、生活費を抑えるコツは固定費を削減することです。固定費は毎月決まった金額が発生します。食費や日用品費のように節約できないのが特長です。
固定費には、以下のものが挙げられます。
・住宅費(家賃・住宅ローン)
・水道光熱費
・通信費
・保険料
・教育費
・車関係費(ローン・駐車場代)
・サブスクリプション
これらは契約の段階でどれだけ抑えられるが大切です。サブスクリプションは使っていないものの見直しや解約をすることですぐに固定費を削減することができますね。
また、通信費は格安SIMのキャリアに乗り換えることで費用を抑えることができます。自宅で利用する場合が多い場合はインターネット回線を引いてしまった方が格段に安く、快適な環境を手にすることも可能となるケースもあります。
節約はムリなく楽しくを意識する
ポイントは「ムリなく楽しく」です。食費で述べたように、一時的な節約は効果は見込めません。また、効果もあまりないでしょう。それではせっかくの節約も意味をなさなくなってしまうので、「ムリをせず行う」ことが大切です。
そして、続けるうえで大切なのは「楽しむ」ことです。楽しいことって長続きしますよね。youtubeやtiktok、インスタグラム、ゲームやアニメなど。楽しいことは長続きします。節約も同じで楽しんで行うことで長続きさせることができ、結果も期待できるようになります。
さいごに
収入のバラつきこそありますが、極端な生活をしなければ基本的な消費支出額の支出バランスはそこまで変化しません。
もしも、乱れた生活があるような場合には、改めて見直すことで使いすぎの原因の特定にも役立ちますので、支出バランスを見て、これからの生活に活かしてみてください。
以上、ぴろ君でした。